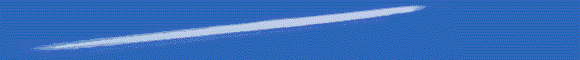
工芸の丘・図書館・京成デ
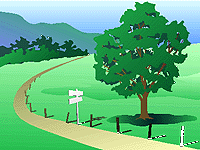
|
笠間工芸の丘 −笠間でやきもの作りをしてみませんか− 笠間工芸の丘では、年に3回*、陶芸教室を開催しています。 手ひねり教室は、 火曜日コース(12回、24,000\)。 ロクロ教室は木曜日コースと金曜日コース(12回、 30,000\)。 やきものの本場で、とっても環境のいい工芸の丘は、のびのびとやきもの 作りが楽しめますよ。 自分で作った皿に干物をのせて、自分で作った徳利とぐい呑み で旨酒を飲む。 どんなに形がいびつであったとしても、こたえられませんね。 一度 やきもの作りをやってみませんか。 何かの本で、磁器の食器は普段用、晴れの日の 食器は陶器で、というのがありました。 何となく賛成の気分です。 上野、南雲の凹凹コンビは、9/7から、2012年秋の陶芸教室 ロクロ金曜日コース を受講しました。 受講を始めてから11年半となり、高校3年生の2学期終了という ところです。 二人にとって、笠間通いは生活の一部となっているので、続けられる限り一番の古株 で居ようと思っています。 最近(H21/10頃)になってやっと、半人前のぐい呑みが 作れるようになりました。 徳利はまだまだです。 H18年冬の教室は、前立腺手術のため参加できず、不受講となってしまいました。 しかし、陶芸教室ポスターのモデルになっていたのには、いささかびっくりです。 笠間工芸の丘では、陶芸教室のほかにも、1日だけの「体験教室」もやっています。 試しに ちょっと出掛けて行って、やきもの作りをしてみませんか。 笠間工芸の丘URL:http://www.kasama-crafthills.co.jp/ *(注) 冬の陶芸教室 : 1月上旬〜4月上旬 夏の陶芸教室 : 5月中旬〜8月上旬 秋の陶芸教室 : 9月上旬〜12月上旬 私がモデルのポスター 半人前のぐい呑み  茨城県立図書館 県立図書館がリニューアルされたのが 2001年3月。旧県庁内の議会館を改築し、 広くて明るい図書館になっています。まだ 行ったことがない人は、是非一度 行って みては如何ですか。 閲覧室にもなっている視聴覚ホールで 静寂の空間の中、自分 だけの至福の時間を過ごすのも、なかなか乙なものです。 この視聴覚ホールでは、音楽会、講演会、映画上映も 頻繁に行われています。 私は この図書館には いつも 自転車で行きます。 片道20分程。 適当な運動を 兼ねて、通っています。 昼食はかみさんが作ってくれる おむすび。 外のベンチで よく食べます。 ・開館時間は平日9:00〜20:00。休館は毎週月曜日。 ・本を借りるための「利用カード」を作ってもらうには、運転免許証、健康保険証、 学生証などの身分証明書の提示が必要。 ・駐車場もあります(入口は郵便局裏側、帰りに駐車券を発行してくれる)。 ・県立図書館URL : http://www.lib.pref.ibaraki.jp 最近読んで面白かった本 ● 「静かに健やかに遠くまで」 城山三郎著 ・はたらくといってね、働くのも、楽のうちなんだよ ・七十を過ぎると、一年一年、生きることが仕事ですよ ● 「定年後すぐボケる人 かえって若返る人」 中島義道著 ・脳の働きにしろ、体の働きにしろ、人間の「実用機能」は加齢と共に右肩下がりに 衰えていくわけではない。 老化現象は死ぬ間際の数年間で急速に進む。 ・頭も体も「使わない機能」は急速に衰える。 ・高齢者の場合、休養は「充電」ではなく「放電」になってしまう。 ・人間にとっては、「感情の老化」こそが、あらゆる老化現象の根源。 「ときめき脳」 が老化を防ぐ。 ・周囲に遠慮することなく、積極的に刺激を求めて自由に行動するのが、本来の 「悠々自適」ではないか。 ● 「川柳うきよ鏡」 小沢昭一著 : ・妻旅行電話も人もぴたり止む ・定年後「家事手伝い」を肩書に ・忘れないように何かに書いたけど ・後半は早足になる美術館 ● 「さいごの約束」 坂本敬子著 : ・’04/2月、夫和彦 がんで死亡、47歳。 後を引き継ぎ、大洗町「月の井酒造」の 社長となる。 ・’02/3月の人間ドックで夫の食道がんが見つかり、少しでもいい病院を探しての、 夫婦での凄絶ながん闘争。 入退院の繰り返し。 ・夫に捧げた有機の酒「和(な)の月」。 和彦の和と月の井の月から命名。 ・大吟醸が美味いのはあたりまえ。 ふだん晩酌に飲めるような価格の酒が美味いと いう蔵元になりたい。・・・和彦 ・「和の月」は’04年の秋に一度飲んだ覚えがあります。 いい酒だったと記憶して います。 今では、2年先まで予約が入っていると聞いています。 月の井酒造は ’05年暮の62会忘年会の後に、皆んなで見学と酒購入に行ってきました。 前夜 からの尿閉状態で苦しい状態中でゆっくり見れなかったので、その内また行って みるつもりです。 ● 「いいクルマの条件」 三本和彦著 : ・車は「自分たちの生活を便利に、楽にするもの」が当たり前の条件。 ・最新の車が最上の車である。 ・日本の特徴ある車・・・ロードスター/セルシオ/コペン/レガシィ/クラウン/シビック ・試乗のチェックポイント・・・細部にとらわれず、家族で乗ってみる/身切りはいいか/ 乗り降りのし易さ/シートの座り心地/操作系の感触/乗り味・乗り心地/音質は許容 範囲か/色の経済性・安全性も考える ● 「音のおもしろ雑学事典」 「音」雑学研究会編 : ・20,000Hz以上が超音波、20Hz以下が低周波 ・気導音は2,000〜3,000Hzが伝えやすく、骨導音は250Hz周辺が伝えやすい。 ・スピーカーシステムの名機・・・日本ビクターのSX−L9 ・音痴は直る・・・表声と裏声を交互に出す練習(ウォーとアー) ● 「名指揮者との対話」 青澤唯夫著 : ・いいオーケストラとか悪いオーケストラというものは(本来)存在しない。 指揮者が その場で創り出すものだ。・・・ チェルビダッケ ・音楽はその場で生まれてくるものだ。 だから、予め存在するものではない。・・・ 同 ・悪いオーケストラはない。 悪い指揮者がいるだけだ。・・・ ハンス・フォン・ビューロー ● 「酒は風」・・・「亀の翁」をつくる人びと 英伸三写真 首藤和弘・英愛子文 : ・新潟県 三島郡 和島村の久須美酒造(夏子の酒のモデル)での酒造り。 ・越後野積杜氏の河井清 名杜氏が飲んで忘れられないといった酒米「亀の尾」。 「亀の尾」は コシヒカリ、ササニシキ、五百万石のルーツ。 育て難いことから、 作られなくなったが、1980年つくばの農水省種子センターにあった1500粒の 種米を取り寄せて、復活が始まった。 そして苦心を重ねて出来上がったのが 幻の 銘酒「亀の翁」。 ・酒はその地において、その地の酒肴とともにある。 ・「亀の翁」とよく合うのは、のど黒の塩焼きやあけびの新芽のおひたし。 ・酒造り工程 : 一麹、ニもと、三醪 ・久須美酒造はH16/7の水害で大きな被害を被ってしまった由。 復興を祈ります。 ● 「国家破産サバイバル読本(上)(下)」 浅井 隆著 : ・日本の公的債務 1,100兆円、GDP 500兆円、個人金融資産1,200兆円。 このままではいずれ国家破産になるのは避けられない。 日本の経済パターンや 外国の事例からみても、2006〜08年には国家破産が表面化してくる。 スーパーインフレや徳政令、治安悪化が襲って来る。 ・ここに書かれていることの起こる確率は分からないなりにも、危険性は十分にある ことから、個人責任で幾分の対策は必要かも知れない。 海外ファンドを薦めて いるが、ちょっと手出しには踏み切れない。 ● 「天才の読み方−究極の元気術」 齋藤 孝著 : ・ピカソ : 精力は使えば使うほど湧いてくる/まねることで人の技を自分のものに する/自分のスタイルにこだわらない/大量の作品は質を低下させない ・宮沢賢治 : 豊かな知識は経験を深め、世界を広げる/自然に身体と心をさらして 自己を鍛える/歩くという技 ・シャネル : 人に迎合しない/シンプルさを押し通す/コンプレックスを武器にする/ お金は自分で稼ぐ/自分を認知させることで人間関係をラクにする ・イチロー : 真の天才は量をこなす(大量に練習することで、質を飛躍的に高め、 集中力を高める)/感謝を自分のパワーにする/つねに原点に立ち返る ● 「読めそうで読めない漢字」 現代言語セミナー編 角川文庫 : ・姦(かしま)しい ・淑(しと)やか ・欠伸(あくび) ・嗽(うがい) ・靨(えくぼ) ・蠢(うごめ)く ・塒(ねぐら) ・簪(かんざし) ・鬼灯(ほうずき) ・雪洞(ぼんぼり) ・鏤(ちりば)める ・擽(くすぐ)ったい ・嬲(なぶ)る ・犇(ひしめ)く ・鏤(ちりば) める ・微睡(まどろ)む ・希(こいねが)う ・泥(なず)む ・十六夜(いざよい) ● 「男の顔は領収書」 藤本義一著 : ・男はまず牡であること−牡の論理−: 攻撃と守護の狩猟本能 ・女は 仕事をしている男に魅かれる。(仕事をサセラレテイル男ではない。) ・昼の酒は残酷、黄昏の酒は郷愁、夜中の酒は陶酔、夜明けの酒は恍惚。 ・女の顔は請求書、男の顔は領収書。 ● 「不安の力」 五木寛之著 : ・人は不安とともに生まれ、不安を友として生きていく。 不安を追い出すことは できないし、不安は決してなくならない。 不安のない人生などというものはない。 ・ちゃんと泣けない人には、腹の底から笑うこともできるわけがない。 ・老いや成熟が悪とされる社会・・・今の日本のカルチャーは全部 若い人の方を 向いている。 → 熟年者は自分達のカルチャーなりファッションなりを確率せよ。 ・経済 :社会のエンジン、アクセル 政治 :ハンドル 宗教 :ブレーキ ● 「二十四の瞳」 壺井栄 著 :H15/2月にかみさんと四国旅行に行き、その時 小豆島を訪れた。 帰ってきてから、改めて、この本を読んでみた。 高峰秀子が 大石先生をやった映画は大好きで、もう何回もTVでも見ました。 ・磯吉は笑いだし、「目玉がなーんじゃで、キッチン。 それでもな、この写真は見え るんじゃ。 な、ほら、まん中のこれが先生じゃろ。 その前に・・・・・・・」 磯吉は確信をもって、そのならんでいる級友のひとりひとりを、人さし指でおさえて みせるのだったが、少しずつそれは、ずれたところをさしていた。 相槌の打てない 吉次にかわって大石先生は答えた。 「そう、そう、そうだわ、そうだ」 あかるい声でいきをあわせている先生の頬を涙の すじが走った。 京成百貨店 長男 達馬の勤務先。 H18−3/17にこれまでの「水戸京成百貨店」から「京成百貨 店」に名前を変えて、新店オープンとなりました。 地上10階・地下2階のビルで、 店舗面積も2.6倍と広くなり、目下水戸近辺の注目を集めています。 かみさんの言に よると、水戸で唯一都会的な所とのこと。 魚売場もお気に入りの様子で、時々徒歩で 買い物に行っています。 結構いつも、人で賑わっているようです。 私としても、長い 間待ち望んでいたので、時々出向き、地下の酒類コーナー辺りをうろうろしています。 これを機に、低迷している商店街が少しでも活気を取り戻してくれるといいなと思って います。 四十数年前、新潟県から移住して来た時は、市電が走り、二つのデパート が向かい合っていて、水戸の中心繁華街でした。 ふと、そんなことを想い出しました。 京成百貨店のホームページは http://www.mitokeisei.co.jp/ |
メール |
トップ |